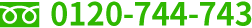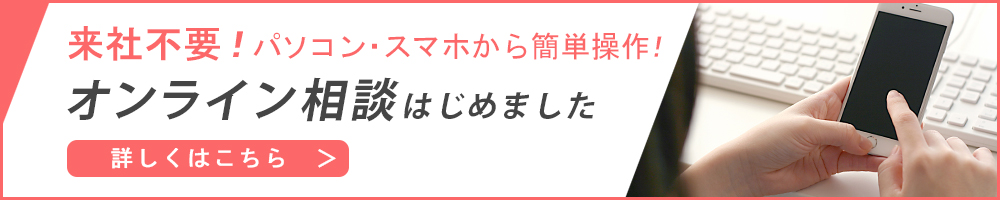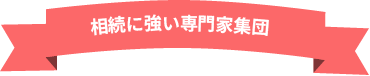遺言だけで相続できる?遺言が無効になり相続が難しくなるケースまとめ
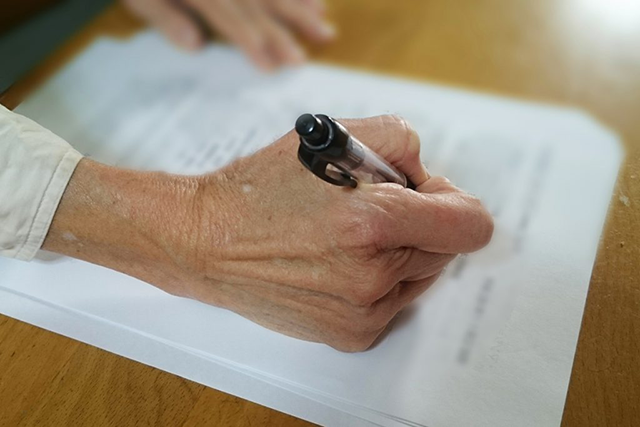
せっかく故人が遺言書を残してくれていても、「その遺言書がそもそも無効なので相続手続きで使えない」というケースがあることはご存知ですか?
実は、遺言書の形式は法律で決められており、その形式に不備があると遺言書が無効となってしまう、もしくは相続のお手続きには使えなくなってしまうことがあるのです。
特に、自筆で書かれた遺言書には、残念ながらご相続のお手続きで使えないものが少なくないのが現状です。では、遺言が無効になり、使えなくなってしまうケースにはどんなものがあるのか、確認してみましょう。
遺言者のお名前・遺言書を書いた日付・遺言者の押印はありますか?
民法第968条には、次のように書かれています。
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
自筆で遺言書を遺す場合、全文を自筆で書くだけでなく、氏名・日付をきちんと書いて、さらに押印(印鑑は必ずしも実印である必要はありません)をしなければ、無効となってしまうのです。「自書」とありますので、代筆も認められません。
ご自分が書かれた遺言書があれば、見直してみてください。そもそも遺言書がパソコンで書かれていたり、誰かに代わりに書いてもらっていたり、氏名・日付が書いていなかったり、印鑑が押されていなかったりしませんか?
内容はご相続人のためによく考えられた「いい遺言書」でも、上記の単純な形式違いだけで遺言書が無効になってしまいますので、気をつけましょう。(今後は改正がされ、自書に頼らない財産目録(パソコンで目録を作成し、通帳のコピーを添付・署名押印をする)を添付することが出来る様になる予定です。)
相続財産の特定は必要十分ですか?
我々が業務の中で拝見する遺言書には、「どの」財産を遺されたのか特定できていない、中でも不動産の特定が不十分な遺言書も見受けられます。
遺言書は、ご自分の「どの」財産を「どなたに」遺されるのか、その遺志を残すためのものです。この遺言書を相続手続き、特に相続登記手続きで使用する場面では、残念ながら遺言を遺された方は亡くなっていますので、その意図が不明な場合でも本人に確認が取れません。ですから、本人亡き後、誰が見ても明らかなように財産を特定しておかなければ、手続きには使えない、ということになってしまうのです。(当たり前といえば当たり前のお話ですが。)
遺言書で不動産を遺される場合には、「東京都千代田区の土地」、「自宅」、「自宅建物」といった記載や「住所~の不動産」といった記載では、残念ながら相続不動産の特定には不十分と言わざるを得ません。
遺言書でご自分の名義の不動産をどなたかに遺されたい場合には、必ず、登記簿謄本(登記事項証明書)で所在、地番、家屋番号など、不動産を特定するのに必要十分な情報を確認して記載しましょう。
遺言者が亡くなった時、相続人が既に亡くなっていたらどうなる?
たとえば遺言者である父が、相続人の長女に自分の名義の自宅不動産を相続させる内容の遺言書を残していたとします。ところが、父より先に相続人の長女が亡くなってしまいました。その後父が亡くなった場合、長女が相続するはずだった父名義の自宅は、どうなるでしょう?
多くの方が、「父の他の相続人が相続することになる」とか「長女の相続人が自動的に権利を取得する」と思われるのではないでしょうか?
実は、遺言書に「先に長女が亡くなった場合」について特に何も書かれていないと、長女が父より先に亡くなった時には、長女に相続させるはずだった遺言書の記載部分のみ、無効となります。父が亡くなった時に、自宅については、遺言書を使って相続手続きをすることはできなくなってしまうわけです。
この場合、長女に相続させるはずだった自宅不動産については、父の相続人全員で遺産分割の協議をするか、法律で定められた割合で長女以外の父の相続人が相続する、ということになります。
相続人のために遺言書を遺されても、必ずしも、相続人より先に遺言者が亡くなるとは限りません。
もし万が一、遺言者より先に財産を相続させるはずだった相続人が亡くなった場合に備えて、遺言書には「予備的遺言」をきちんと遺しておくべきです。
予備的遺言とは、もし遺言者より先に財産を相続させるはずだった相続人が亡くなっていた場合には、その財産を別の相続人に相続させる、などとあらかじめ決めておくことを言います。
冒頭の例で言えば、もし父より先に相続人の長女が死亡していた場合には、長女に相続させるはずだった財産は、他の相続人である長男に相続させる旨などを遺言書に書いておくのです。
そうすれば、長女が父より先に亡くなっていても、父の遺した遺言書を使って、長男は相続登記の手続きをすることができるようになります。
遺言書が無効な場合、相続手続きはどうなるか?
遺言書が残っていたものの、方式に不備があったり、内容が不十分で相続手続きに使えないケースは少なくありません。
遺言書が相続手続きに使えなくなった場合には、相続人全員で遺産分割(遺産分け)の協議をする必要が出てきます。
この遺産分割の協議が、なかなか厄介です。
相続人全員が健在で、コミュニケーションが取れ、争いもなく協議が終わるケースももちろんあります。ですが、中には相続人の何人かと連絡が取れないとか、相続人が認知症になって協議ができないなど、協議がまとまらないケースも出てきます。
まとめ
将来、相続人全員での遺産分割の協議がうまくまとまりそうにない。そもそも相続人と連絡が取れない、協議ができないなどの事情がある。
このように、相続の手続きが難航しそうな場合に、遺言書が遺されていれば相続人の負担もかなり軽減されることになりますが、そもそも遺言書が問題なく手続きで使えるものでなければなりません。
遺言書が無効で手続きに使えず、相続人が困ったことになる前に、専門家に相談されることをおすすめ致します。遺言書のことでご不明なことがありましたら、ご遠慮なく、おおさか法務事務所までお問い合わせください。